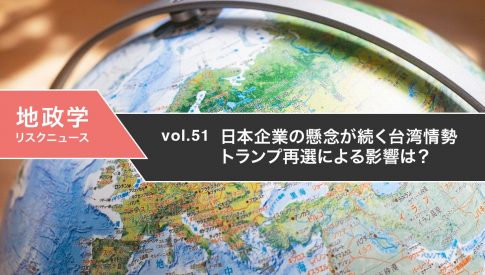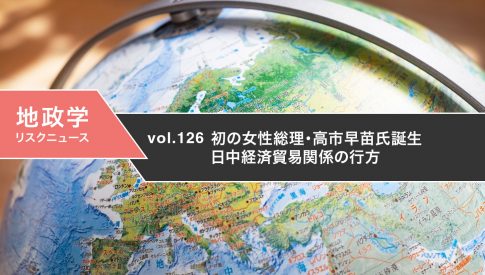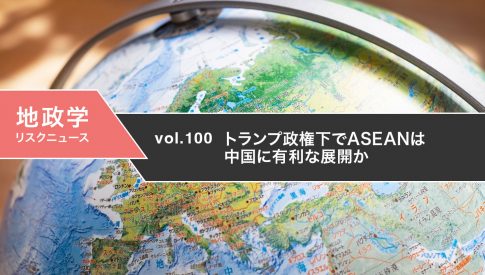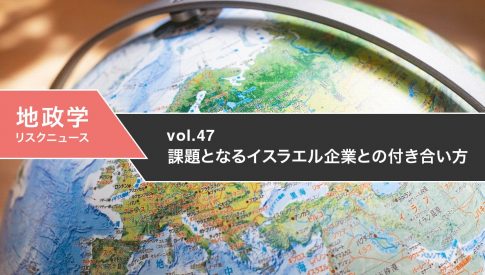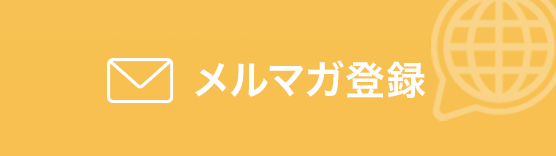もくじ

エクスレバン
これまで渡航した国は40カ国以上 大学時代から国際経済を学び、現地に赴いて調査を行ったり、政治や経済について執筆活動を行っている。趣味はサーフィンと妻とショッピング。コロナ禍が終わりを迎えるなか、今後は中東やアフリカ方面への現地取材を検討中。
※掲載記事につきましては調査時、投稿時に可能な限り正確を期しておりますが、時間の経過とともに内容が現状と異なる場合がございます。
※掲載記載の内容は、弊社の立場や意見を代表するものではありません。
※提供する情報を利用したことによって引き起こされた損害について、弊社は一切の責任を負いません。
近年、日中台の関係は地政学的緊張を帯び、台湾をめぐる議論が活発化しています。日本人として、台湾に親近感を持つ一方で、中国の視点を理解する機会は少ないのではないでしょうか。
本記事では、中国にとって台湾が「国内問題」であるという認識を中心に、その背景と国際法的な側面を解説します。

中国の公式立場:台湾は「不可分の領土」
中国政府は、台湾を自国領土の不可分の一部と位置づけています。これは「一つの中国」原則に基づき、1949年の内戦以降、台湾を統治する中華民国政府を「反乱勢力」と見なし、統一を国家の核心的利益としています。
中国は台湾を香港やマカオと同様の「特別行政区」として再統合すべき存在と考え、独立志向の動きを国内の分裂行為とみなします。この視点から、台湾海峡での軍事演習は「内政防衛のための訓練」とされ、外部の批判は「内政干渉」と一蹴されます。
台湾有事の国際法的位置づけ:中国視点では「違反なし」

台湾有事(中国による台湾への軍事行動)の国際法的な解釈も重要です。中国の立場では、台湾は自国領土内であるため、軍事行動は「内乱鎮圧」や「領土回復」にあたり、侵略や戦争には該当しません。国際法の武力不行使原則は他国への侵略を禁じますが、台湾を「他国」と見なさない中国にとって、この規定は適用されないとされます。中国は「台湾統一は平和優先だが、武力排除せず」との立場を維持しています。
一方、国際社会の多くは台湾を実質的な独立国家とみなし、軍事侵攻を国際法違反とみなすでしょう。しかし、中国の「内政論」を無視すると、地政学的リスクの評価が偏る恐れがあります。
日本人の認識ギャップ:台湾を「別の国」として見る傾向
日本人の多くは、無意識のうちに、台湾と中国を別の国と認識しています。台湾の民主主義や文化的な親和性が背景にあり、観光や食文化を通じた交流も盛んです。しかし、この認識は中国の公式立場と大きく異なり、日中関係の摩擦を助長する要因となっています。
日本政府は台湾を「重要なパートナー」としつつ、中国の「一つの中国」原則を尊重する二重のスタンスを取っています。このギャップを埋めない限り、日本は米中間の板挟みに陥りやすく、台湾有事では「中国の内政干渉」と非難されるリスクもあります。
台湾ビジネスを考える上で:中国認識の理解が鍵
日本企業にとって、台湾は半導体産業の要であり、TSMCなどの供給チェーンは不可欠です。しかし、中国市場とのつながりが深い企業は、台湾有事のリスクを無視できません。有事発生時には、サプライチェーンの断絶や中国からの経済制裁(例:日本製品の輸入制限)が予想されます。
中国の「国内問題」認識を理解することは、ビジネス戦略に不可欠です。中国側から見れば、台湾企業は「中国企業」の一部であり、日台連携は「内政干渉」と映る可能性があります。
企業は、台湾を単なる「安全な投資先」と見なすのではなく、中国の視点を取り入れたシナリオプランニングを進めるべきです。たとえば、台湾有事の抑止策として、日米台の非公式連携を強化しつつ、中国との対話チャネルを維持する多角的アプローチが有効でしょう。
バランスの取れた視野で未来を
中国の台湾認識を理解することは、日本人にとって重要です。両者のギャップを認識することで、より現実的な外交・ビジネス戦略が生まれます。
台湾有事が「内政問題」として国際法違反を免れる可能性を念頭に置き、日本企業は台湾ビジネスを考えるべきでしょう。