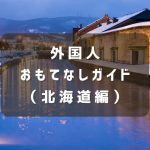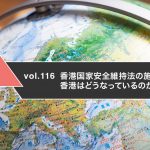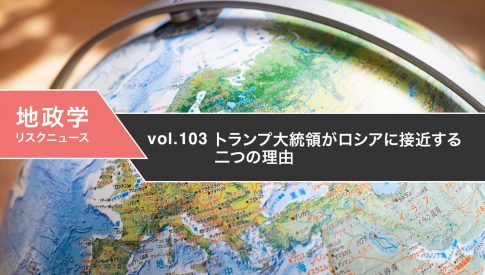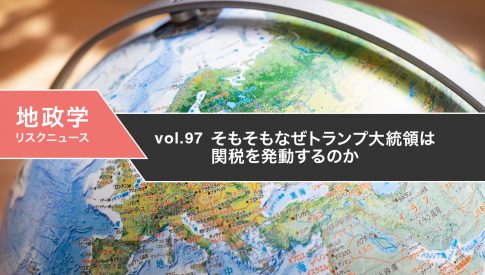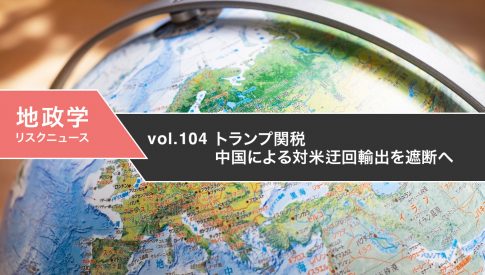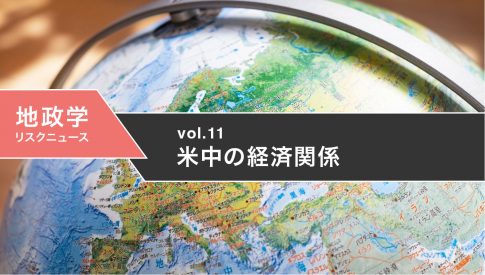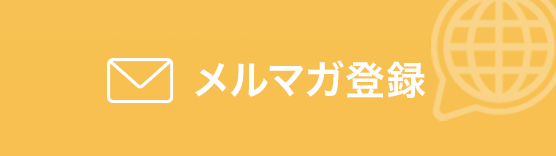エクスレバン
これまで渡航した国は40カ国以上 大学時代から国際経済を学び、現地に赴いて調査を行ったり、政治や経済について執筆活動を行っている。趣味はサーフィンと妻とショッピング。コロナ禍が終わりを迎えるなか、今後は中東やアフリカ方面への現地取材を検討中。
※掲載記事につきましては調査時、投稿時に可能な限り正確を期しておりますが、時間の経過とともに内容が現状と異なる場合がございます。
※掲載記載の内容は、弊社の立場や意見を代表するものではありません。
※提供する情報を利用したことによって引き起こされた損害について、弊社は一切の責任を負いません。
最近、東シナ海上空で中国軍機が航空自衛隊(空自)の機体に異常接近する事案が相次いでいます。2025年7月9日と10日には、中国軍のJH7戦闘爆撃機が空自のYS11EB情報収集機に約30~60メートルの至近距離まで接近し、繰り返し追尾する行動が確認されました。
このような事案は6月にも発生しており、太平洋上空で海上自衛隊(海自)のP3C哨戒機に対し、中国海軍空母「山東」から発艦したJ15戦闘機が約45メートルまで接近したり、前方を横切ったりする危険な飛行を行いました。
これらの行動は偶発的な衝突を誘発するリスクを孕み、日本政府は中国側に深刻な懸念を表明し、再発防止を強く申し入れています。こうした中国軍機の行動の背景には、どのような狙いがあるのでしょうか。

海洋大国としての存在感を誇示する中国

中国海軍は近年、空母「遼寧」と「山東」を中心に太平洋での活動を拡大しています。2025年6月には、両空母が初めて同時に太平洋に進出し、沖縄や小笠原諸島周辺で活動しました。防衛省はこれを異例と捉え、詳細な航路を公表するなど強い警戒感を示しています。
特に「山東」は、沖ノ鳥島付近や南鳥島周辺の日本の排他的経済水域(EEZ)内での航行が確認され、艦載機の発着訓練や戦闘機の活動も活発化しています。これは、中国が「第一列島線」(日本列島からフィリピンに至る線)を超え、「第二列島線」(グアムやサイパンに至る線)での作戦能力を強化する戦略の一環とみられます。
このような空母の展開は、中国が「海洋大国」としての存在感を誇示し、遠洋での軍事作戦能力を向上させる意図を示しています。多くの専門家は、中国が米国やその同盟国の軍事プレゼンスに対抗し、西太平洋での影響力を拡大しようとしていると指摘します。空母の活動範囲が広がることで、中国は遠距離での航空戦力運用能力を強化し、地域の軍事バランスに変化をもたらそうとしているのです。
複数の戦略的意図
中国軍機が自衛隊機に接近する行動には、複数の戦略的意図が考えられます。まず、自衛隊の警戒監視活動に対する牽制が挙げられます。海自のP3C哨戒機や空自のYS11EBは、中国空母や艦艇の動向を監視する任務を担っています。中国側は、これらの活動を妨害し、情報収集を制限することで、自らの軍事行動の自由度を確保しようとしている可能性があります。
次に、軍事的な示威行為としての側面です。中国軍機の接近は、単なる監視の妨害に留まらず、日本や米国を含む同盟国に対して軍事力の存在感を示すメッセージと解釈できます。特に、空母「山東」から発艦したJ15戦闘機がミサイルを搭載していたことが確認されており、戦闘能力を誇示する意図がうかがえます。このような行動は、中国が「ここは中国の空だ」と主張するかのような姿勢を示すものです。
さらに、偶発的衝突のリスクを意図的に高めることで、相手国の対応を試す意図も考えられます。中国軍は近年、米軍やオーストラリア軍機に対しても同様の挑発行為を繰り返しており、2023年には米軍機への異常接近が180件以上あったと報告されています。このような行動は、相手国の反応や危機管理能力を観察し、緊張を高めることで地域の軍事バランスを自国に有利に導こうとする戦略の一環とみられます。
安全保障環境への影響は
中国軍機の接近事案は、東シナ海や西太平洋の安全保障環境に深刻な影響を与えています。
約30~45メートルという至近距離での飛行は、乱気流によるエンジン異常や衝突の危険を伴い、偶発的な軍事衝突のリスクを高めます。日本政府は、外交・防衛ルートを通じて中国側に再発防止を求めていますが、中国側は逆に「日本の艦船と航空機が安全上のリスクをつくり出した」と主張し、対抗姿勢を示しています。このような対立は、日中間の緊張を一層高める要因となっています。
また、中国の空母展開と軍機の挑発行為は、米国やその同盟国の軍事プレゼンスが相対的に弱まる「力の空白」を利用しているとの見方もあります。特に、トランプ政権下での米軍の西太平洋での展開縮小が、中国の活動活発化を後押ししている可能性が指摘されています。この状況下で、日本は自衛隊の警戒監視活動を強化しつつ、米国や他の同盟国との連携を深める必要があるでしょう。
まとめ
日本政府は、これらの事案に対し、外交ルートを通じて抗議を繰り返し、警戒監視活動の継続を強調しています。防衛省は中国軍機の写真や航路を公開し、透明性をもって対応することで国際社会の理解を求める姿勢を示しています。しかし、中国側の反応は不明確であり、緊張緩和に向けた実効的な対話が求められます。
今後、中国の空母運用能力の向上に伴い、同様の事案が増加する可能性があります。日本の自衛隊は、情報収集と監視活動を継続しつつ、偶発的衝突を避けるための危機管理体制を強化する必要があります。また、日米同盟や豪州などとの多国間協力により、地域の軍事バランスを維持し、中国の挑発行為に対抗する戦略が不可欠です。