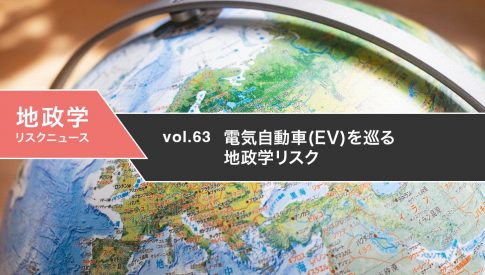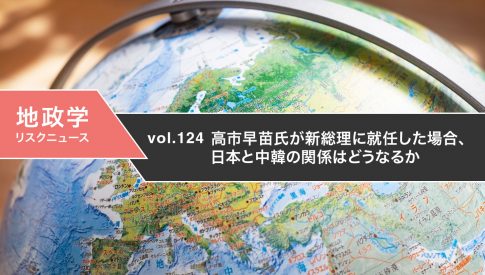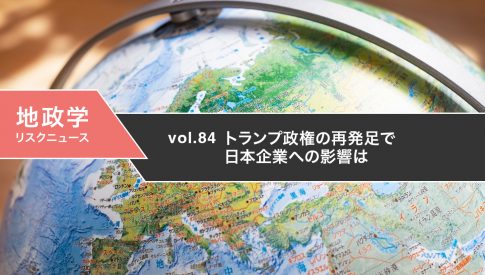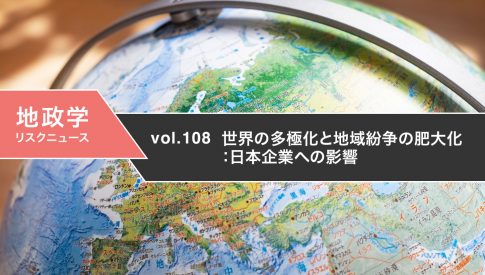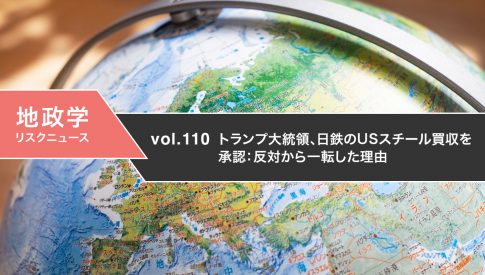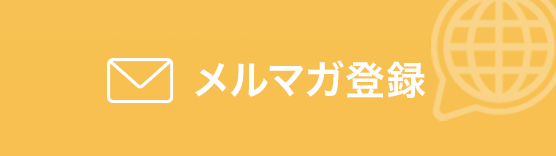エクスレバン
これまで渡航した国は40カ国以上 大学時代から国際経済を学び、現地に赴いて調査を行ったり、政治や経済について執筆活動を行っている。趣味はサーフィンと妻とショッピング。コロナ禍が終わりを迎えるなか、今後は中東やアフリカ方面への現地取材を検討中。
※掲載記事につきましては調査時、投稿時に可能な限り正確を期しておりますが、時間の経過とともに内容が現状と異なる場合がございます。
※掲載記載の内容は、弊社の立場や意見を代表するものではありません。
※提供する情報を利用したことによって引き起こされた損害について、弊社は一切の責任を負いません。
トランプ米大統領が導入した「相互関税」は、ASEAN諸国に高い関税を課す政策として注目されています。
カンボジア49%、ベトナム46%、タイ36%など、関税率は高く、米国市場に依存するASEAN経済に大きな影響を与えます。この政策は、ASEANと中国の関係強化を促す可能性があります。

トランプ関税がASEAN経済に与える影響
まず、トランプの関税がASEAN経済に与える影響を考えてみましょう。
ASEAN諸国は米国への輸出に大きく依存しています。ベトナムは米中貿易摩擦を背景に米国向け輸出を増やし、タイやインドネシアも農産品や電子機器で米国市場を重視してきました。しかし、高関税により米国への輸出品はコスト増に直面し、競争力が低下します。これにより、輸出収入の減少や経済成長の鈍化が懸念されます。関税発動後、アジアの株式市場は下落し、ASEAN経済への不安が高まっています。
この状況で、ASEAN諸国は新たな市場やパートナーを模索します。ここで中国が注目されます。中国はASEAN最大の貿易相手国で、2024年の貿易総額は約1兆ドルです。RCEP(地域包括的経済連携協定)により、ASEANと中国は低関税で貿易を進めており、経済的基盤は強固です。米国市場が閉ざされつつある今、ASEANは中国市場への依存を強め、輸出先や投資先としての中国の重要性が増すでしょう。
中国側の視点も重要です。中国もトランプ政権による125%の関税に直面し、米国市場での競争力が低下しています。そのため、中国は新たな輸出先やサプライチェーンの再構築を急ぎます。ASEANは地理的に近く、労働コストが低い上に、RCEPや一帯一路構想で中国と連携しています。中国企業は、米国への直接輸出が難しい中、ASEANに生産拠点を移し、そこから他市場への輸出を拡大する戦略を進める可能性があります。
過去の米中貿易摩擦でも、ベトナムやカンボジアへの工場移転が見られました。トランプの関税は、この動きを加速させるでしょう。
他のASEAN諸国の状況は

また、地政学的要因も関係強化を後押しします。トランプ政権の「アメリカ第一」政策は、同盟国を含む国々に圧力をかけ、ASEANと米国の関係を不安定にしています。ASEAN諸国は、中国との協力を通じて経済的安定や地域での影響力を確保しようとするかもしれません。
例えば、中国はカンボジアで海軍基地を支援し、ベトナムやマレーシアとも経済協力を深めています。2025年4月の習近平国家主席のASEAN訪問でも、関係強化が強調されました。トランプの関税による経済的圧力は、ASEANの中国接近を後押しします。
しかし、課題も存在します。まず、南シナ海の領有権問題です。中国とベトナムやフィリピンの対立は、信頼関係の構築を難しくしています。
また、ASEANは中国への過度な依存を警戒します。中国の経済的影響力が増すと、政治的影響力も強まり、ASEANの自主性が損なわれる恐れがあります。それでも、トランプの関税による経済的圧力が差し迫っているため、短期的には中国との協力を優先せざるを得ません。
経済的視点では、ASEANと中国の関係強化はサプライチェーンの再編にも影響します。
米国市場が閉ざされれば、ASEANは中国を中心としたアジア内需市場や、EU、中東などを開拓する必要があります。中国は一帯一路を通じてこれらの市場へのアクセスを提供でき、ASEANが中国企業を受け入れることで地域の生産能力が向上します。これは、アジア経済圏の自立性を高める可能性があります。トランプ関税が、意図せずアジアの経済統合を加速させるかもしれません。
また、トランプ関税はEUや日本にも影響を与え、これらの国がASEANや中国と新たな貿易協定を模索する可能性があります。
まとめ
以上の点を踏まえると、トランプの相互関税は、ASEANに米国市場からの離脱を強いる一方で、中国との経済的・地政学的関係を強化するきっかけとなります。
ASEANは、中国市場へのアクセス拡大や投資受け入れで経済的打撃を緩和しようとするでしょう。南シナ海問題や依存リスクは制約ですが、トランプ政権の通商政策が続く限り、ASEANと中国の結びつきは深まる可能性が高いです。この動きは、アジアの経済地図を変える一歩となるかもしれません。