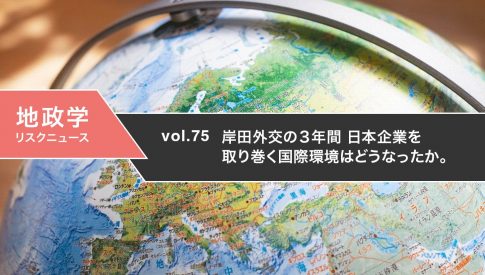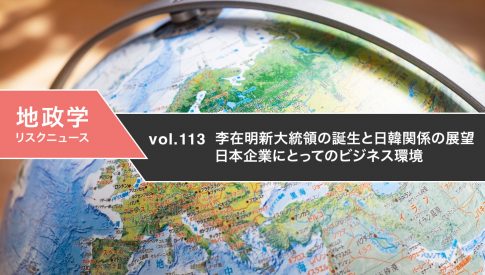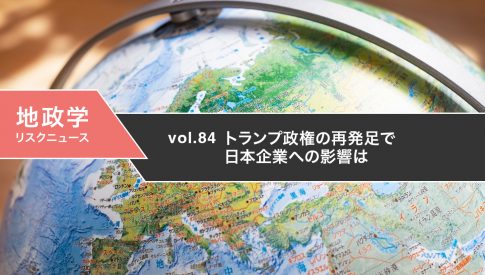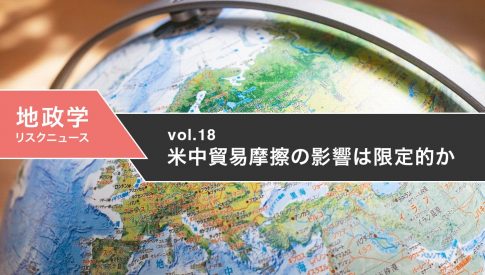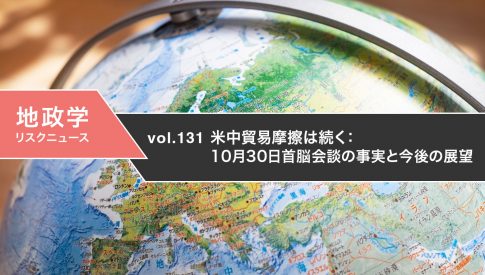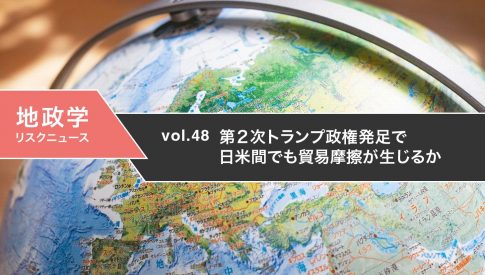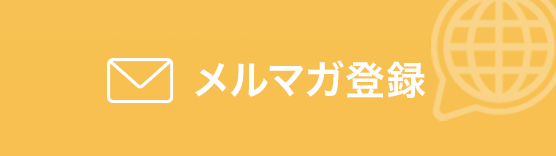エクスレバン
これまで渡航した国は40カ国以上 大学時代から国際経済を学び、現地に赴いて調査を行ったり、政治や経済について執筆活動を行っている。趣味はサーフィンと妻とショッピング。コロナ禍が終わりを迎えるなか、今後は中東やアフリカ方面への現地取材を検討中。
※掲載記事につきましては調査時、投稿時に可能な限り正確を期しておりますが、時間の経過とともに内容が現状と異なる場合がございます。
※掲載記載の内容は、弊社の立場や意見を代表するものではありません。
※提供する情報を利用したことによって引き起こされた損害について、弊社は一切の責任を負いません。
トランプ政権の発足から2ヶ月が経過しましたが、そのウクライナ政策やトランフ関税に諸外国の間では動揺や混乱が広がっています。
そして、今後は中国政策に本腰を入れていくと予測されますが、その中核を占める問題の1つが、半導体をめぐる覇権競争でしょう。
それによって、最近関係の改善が進んでいたように見える日中関係が、再び冷え込む可能性があります。

トランプ政権の強硬姿勢と日本が直面する状況
トランプ氏は1期目において、中国への技術流出を防ぐため、ファーウェイなどの企業に対する輸出規制を強化しました。2期目では、この路線をさらに推し進め、同盟国に対しても対中規制への同調を強く求めることでしょう。
例えば、日本やオランダに対し、半導体製造装置のメンテナンスや輸出制限を強化するよう圧力を掛けることが予想されます。これは、米国の安全保障と経済的優位性を確保し、中国の技術進化を抑え込む戦略の一環です。
バイデン政権が多国間協調を重視したのに対し、トランプ政権は二国間交渉を優先し、経済的報復をちらつかせて同盟国を従わせる傾向があります。この強硬姿勢が、日本にとって新たな試練となるのです。
次に、日本が直面する状況を具体的に見ます。日本は半導体産業において世界的強みを持ち、東京エレクトロンや信越化学工業などの企業がグローバル市場で重要な役割を果たしています。しかし、これらの企業は中国市場に依存する部分も大きく、特に半導体製造装置や材料の輸出で利益を上げています。
トランプ政権が対中輸出規制を強化した場合、日本企業は米国の方針に従わざるを得ず、中国への輸出が制限される可能性があります。これにより、中国市場での売上が減少すれば、日本企業の収益基盤が揺らぎます。
さらに、中国側が報復措置として日本からの輸入を減らす、あるいは日本製品をボイコットする動きに出れば、日中間の貿易摩擦が一気に高まるでしょう。
日中の経済関係はどうなっていくのか

このような状況が、日中の経済関係悪化を招くことが懸念されます。
日中両国は、経済的に相互依存関係にあります。2024年時点で、中国は日本の最大の貿易相手国であり、日本からの輸出品には半導体関連製品が含まれています。一方、日本は中国から電子機器や部品を輸入しており、サプライチェーンの結びつきが深いです。
しかし、トランプ政権の同調圧力により、日本が対中輸出を制限すれば、中国側は経済的報復を検討する可能性があります。例えば、中国がレアアースの輸出を制限する過去の事例を踏まえれば、日本企業への供給網が寸断されるリスクも考えられます。このような報復の連鎖は、日中間の信頼関係を損ない、経済的緊張を増幅させます。
さらに、トランプ政権の政策は、日本企業に戦略転換を迫ります。短期的には中国市場の縮小とコンプライアンス負担が増加し、長期的には米中双方との関係を見直す必要が生じるかも知れません。日本は、米国との同盟関係を維持しつつ、中国との経済的結びつきをどう保つかのジレンマに直面します。
リスク分散のため、東南アジアやインドへの進出を強化する動きが加速するかもしれませんが、新市場へのシフトには時間とコストがかかります。その間、日中貿易の縮小が進めば、両国経済に悪影響が及ぶことは避けられません。
一方で、楽観的な見方も存在します。日本が米国の規制に全面協力すれば、日米関係が強化され、米国市場でのシェア拡大が期待できるかもしれません。
しかし、これは中国との関係悪化を代償とするものであり、全体としての経済的損失を補うには不十分です。トランプ政権の予測不能な外交スタイルを考慮すれば、日本が米国の方針に盲目的に従うリスクも見逃せません。
まとめ
以上の点を踏まえると、トランプ政権下の半導体覇権競争は、日中の経済・貿易関係悪化の引き金となる可能性が高いです。米国からの同調圧力、中国からの報復リスク、そして日本企業への戦略的負担が重なり、両国間の経済的緊張が強まります。
日本は技術力と外交力を駆使してこの危機を乗り越える必要がありますが、対応を誤れば、米中対立の狭間で深刻な打撃を受けるでしょう。半導体産業の未来は、米中の動向と日本の選択に大きく左右されると言えるでしょう。