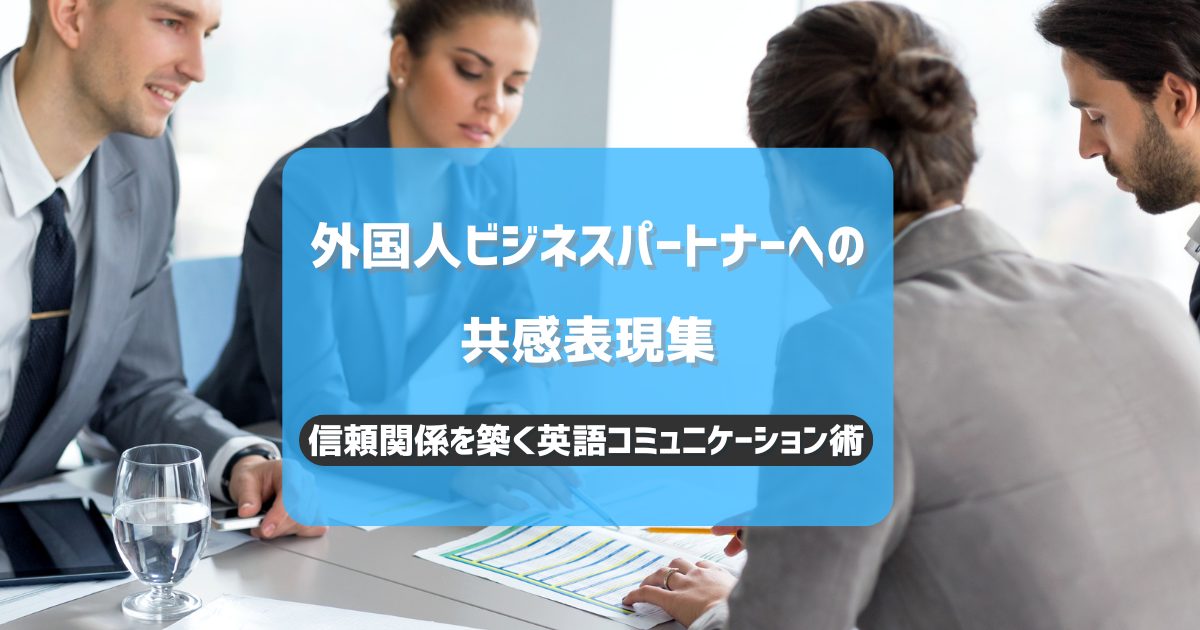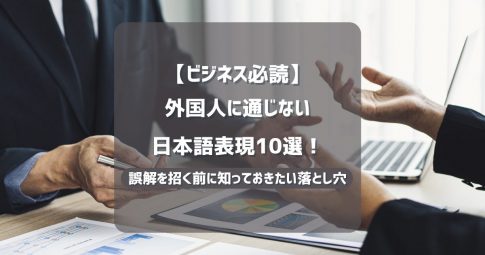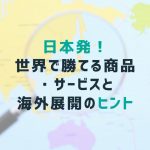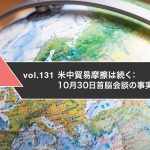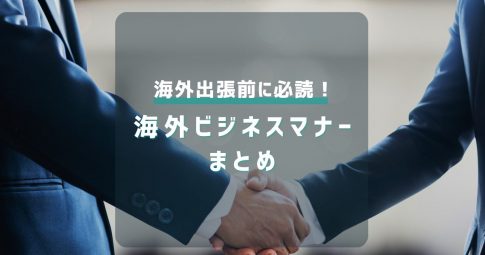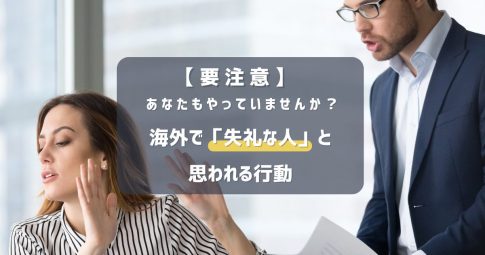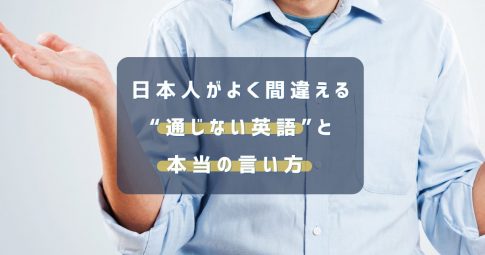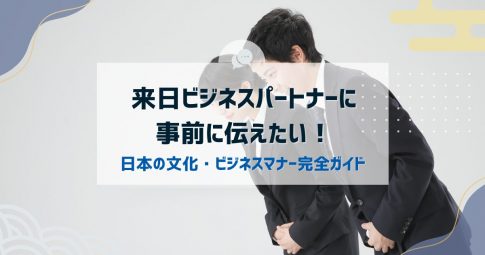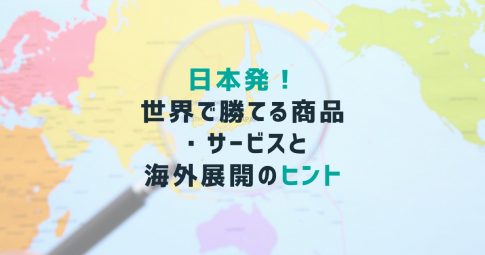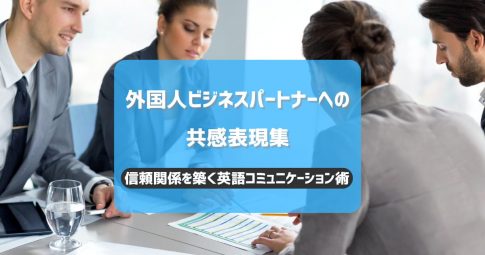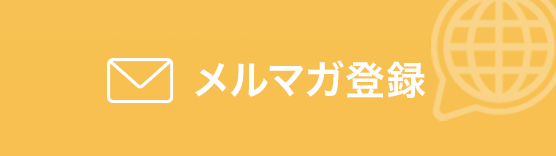もくじ
グローバルビジネスにおいて、専門知識やスキルと同じくらい重要なのが「共感を適切に表現する力」です。日本語では「そうですね」「大変でしたね」といった短いフレーズで相手への理解を示すことができますが、英語でのビジネスコミュニケーションでは、より具体的で明確な表現が求められます。
ビジネスにおける共感力は、チームのパフォーマンスや顧客満足度に直結するとも言われており、特に多文化環境では、言語の壁があるからこそ、意識的に共感を言語化することが信頼関係構築の鍵となります。
適切な共感表現は、単なる社交辞令ではなく、相手の状況を理解し、協力関係を深めるための戦略的なコミュニケーションツールなのです。
よく使われる基礎フレーズとその使い分け
ビジネスシーンで最も頻繁に使われる共感表現として、”I understand”と”I see what you mean”があります。”I understand”は相手の言っていることの内容を理解したときに使い、”I see what you mean”は相手の意図や背景まで含めて理解したことを示します。
“That makes sense”は、相手の説明や論理に納得したときに使える便利な表現です。会議中に相手の提案を聞いた後、「なるほど、理にかなっていますね」という意味で頻繁に使われます。
“I can imagine…”は、自分が直接経験していない状況でも、相手の立場に立って共感する姿勢を示すことができる表現です。例えば、”I can imagine how challenging that must be”(それがどれほど困難か想像できます)のように使います。
興味深いことに、「聞いている」というサインを送ることの重要性は、日本でも海外でも共通しています。ただし、日本では沈黙や頷きで示すことが多いのに対し、英語圏では言語化して伝えることが期待されます。
シーン別実践フレーズ集
ここからは下記4つのシーンに分けて共感フレーズをご紹介していきます。
- 意見や提案への反応
- 困難や課題に対する共感
- 相手の成功を祝う・喜びを共有する
- ミスやトラブル発生時
海外ビジネス情報をお届け

意見や提案への反応
相手の意見や提案に対する共感的な反応は、建設的な議論の基盤となります。”That’s a great point”(それは素晴らしい指摘ですね)は、相手の発言の価値を認める表現で、会議やディスカッションで頻繁に使われます。
“I really appreciate your perspective”(あなたの視点に感謝します)は、自分とは異なる意見でも、その価値を認めることを示します。多様性を尊重するグローバル企業の文化において特に重要な表現です。
“You’ve raised an important concern”(重要な懸念点を提起していただきました)は、相手の問題提起を真摯に受け止めていることを伝えます。リスク管理や品質改善の議論で効果的です。
困難や課題に対する共感
相手が直面している困難に対しては、理解と支援の姿勢を明確に示すことが大切です。”That sounds challenging”(それは困難そうですね)は、相手の苦労を認識していることを伝える基本的な表現です。
“I can see why that would be frustrating”(それがフラストレーションになる理由がわかります)は、相手の感情に寄り添う表現です。納期の遅延やシステムトラブルなど、業務上のストレス要因について話すときに使えます。
“That must have been difficult”(それは大変だったでしょう)は、相手が既に経験した困難に対する共感を示します。過去形を使うことで、その困難が一段落したことも暗に示すことができます。
相手の成功を祝う・喜びを共有する
ビジネスパートナーの成功や良いニュースには、積極的に喜びを表現することが重要です。”That’s fantastic news!”(それは素晴らしいニュースですね!)は、相手の達成を心から祝福する際に使える表現です。
“I’m so glad to hear that”(それを聞けて本当に嬉しいです)は、相手の報告に対する肯定的な反応を示します。プロジェクトの進捗報告や問題解決の知らせを受けたときに効果的です。
“Congratulations on…”(~おめでとうございます)は、昇進、契約獲得、プロジェクト完了など、具体的な成果に対して使います。例えば、”Congratulations on closing the deal”(契約成立おめでとうございます)のように使用します。
ミスやトラブル発生時
ミスやトラブルが発生したときこそ、適切な共感表現が関係性を維持する鍵となります。”These things happen”(こういうことは起こるものです)は、相手を責めずに状況を受け入れる姿勢を示します。
“I completely understand the situation”(状況を完全に理解しています)は、相手の置かれた立場や背景を踏まえて対応することを伝えます。特にクライアントとのトラブル対応で重要です。
“Let’s figure this out together”(一緒に解決策を見つけましょう)は、問題解決への協力姿勢を示す前向きな表現です。責任の追及ではなく、解決に向けて協働する意思を明確にします。
微妙なニュアンスが伝わるか不安な重要な場面では、プロの通訳サービスの活用も検討しましょう。特にクレーム対応や契約交渉では、適切な共感表現が関係性を左右します。経験豊富な通訳者は、文化的背景を踏まえた最適な表現を選択し、誤解を防ぐサポートをしてくれます。重要な商談の前にリハーサルを行うことで、自信を持って本番に臨むことができます。
「共感を示す」際の注意点
共感を現すことはコミュニケーションにおいて、お互いの共通理解や意思疎通を示すために必要なことである一方、いくつか注意が必要な場面や背景があります。
過度な共感は逆効果になることも
グローバルビジネスの現場で働いてみると、日本式の「寄り添い」がすべての文化で歓迎されるわけではないことがわかります。特に欧米のビジネス文化では、過度な共感は時として不誠実さや決断力の欠如と受け取られることがあります。
“I know exactly how you feel”(あなたの気持ちが正確にわかります)という表現は、使用に注意が必要です。相手の状況を完全に理解していないのにこのフレーズを使うと、軽薄な印象を与える可能性があります。代わりに、”I can imagine…”や”That sounds…”のように、ある程度の距離を保った表現の方が適切です。
日本のビジネス文化では「察する」ことが美徳とされ、言葉にしなくても相手の気持ちを理解することが期待されます。一方、多くの国際ビジネス環境では、言語化して明確に伝えることが信頼の証とされます。この違いを理解することが、効果的なコミュニケーションの第一歩です。
文化による反応の違いを理解する
北米のビジネス文化では、一般的にポジティブな反応が好まれる傾向があります。”That’s great!”や”Sounds good!”など、明るく前向きな表現が日常的に使われます。ただし、これらが必ずしも深い賛同を意味するわけではなく、会話をスムーズに進めるための潤滑油的な役割を果たしていることも理解しておく必要があります。
欧州、特に北欧や中欧のビジネス文化では、控えめでありながらも具体的な共感表現が好まれます。過度に感情的な表現よりも、”I understand your position”(あなたの立場を理解します)のように、論理的で冷静な反応が適切とされることが多いです。
興味深いことに、アジア圏のビジネス文化には日本との共通点も多く見られます。階層を重視し、直接的な対立を避け、調和を大切にする価値観は、中国、韓国、シンガポールなどでも共有されています。ただし、シンガポールのように英語が公用語の国では、欧米式の明確なコミュニケーションとアジア的な配慮が融合したスタイルが見られます。
海外ビジネス情報をお届け

ボディランゲージとの組み合わせ
共感を効果的に伝えるには、言葉だけでなくボディランゲージも重要です。オンライン会議が主流となった現在、カメラを通じた非言語コミュニケーションがより意識的に求められています。
適度な頷きは、世界中のビジネス文化で「理解している」「同意している」サインとして機能します。ただし、日本では相槌が非常に頻繁に行われるのに対し、欧米では頷きの頻度は少なめで、重要なポイントでのみ明確に頷くことが一般的です。
アイコンタクトの取り方も文化によって異なりますが、ビジネスの場では適度なアイコンタクトが信頼性を高めることは世界共通です。オンライン会議では、カメラを見ることで相手とのアイコンタクトを模擬できます。話を聞いているときは画面を見て、話すときは時々カメラを見るというバランスが効果的です。
メールやチャットでの共感表現に悩んだら、翻訳サービスで複数の表現パターンを確認するのも効果的です。単なる機械翻訳ではなく、文化的背景を理解した翻訳者のアドバイスは、独学では得られない価値があります。特に重要なメールを送る前に、ネイティブチェックを受けることで、意図しない誤解を防ぎ、プロフェッショナルな印象を与えることができます。また、過去の成功事例や失敗事例から学ぶことで、自分自身の表現力も向上していきます。
一歩進んだ共感テクニックにチャレンジ
先にご紹介した英語表現以外にも、下記の方法で共感を伝える方法があります。それぞれのテクニックを用いることで、単なる共感で終わらず、その後の会話・ディスカッションを前進させることにも繋げることができます。
パラフレーズで理解を示す
より高度な共感テクニックとして、パラフレーズ(言い換え)があります。相手の発言を自分の言葉で言い換えることで、正確に理解していることを示すことができます。
“So what you’re saying is…”(つまり、あなたが言っているのは…)は、相手の話を要約して確認する表現です。これにより、誤解を防ぎながら、相手の意見を尊重していることを示せます。
“If I understand correctly…”(私の理解が正しければ…)は、自分の解釈を確認する際に使います。相手に訂正の機会を与えることで、より正確なコミュニケーションが可能になります。
海外ビジネス情報をお届け

質問で共感を深める
適切な質問は、共感をさらに深める強力なツールです。”How did that make you feel?”(それについてどう感じましたか?)は、相手の感情面に焦点を当てた質問で、信頼関係を構築する上で効果的です。
“What would be most helpful for you right now?”(今、あなたにとって最も役立つことは何でしょうか?)は、実質的なサポートを提供する意思を示す質問です。共感を行動に移すための橋渡しとなります。
これらの質問は、単に情報を得るためだけでなく、相手に「あなたのことを本当に理解したい」というメッセージを送ることができます。
未来志向の共感で前進する
問題や困難に対する共感だけでなく、解決に向けた前向きな姿勢を示すことも重要です。”Let’s work on a solution together”(一緒に解決策に取り組みましょう)は、協力関係を強調しながら建設的な方向性を示します。
“I’m confident we can overcome this”(私たちはこれを乗り越えられると確信しています)は、困難な状況でも希望と信頼を表現する力強い言葉です。リーダーシップを発揮しながら、チームの士気を高める効果があります。
未来志向の共感は、単に相手の気持ちに寄り添うだけでなく、次のステップへと導く推進力となります。グローバルビジネスでは、この「共感しつつ前進する」バランス感覚が特に重要です。
まとめ
外国人ビジネスパートナーとの効果的なコミュニケーションにおいて、共感表現は単なる社交辞令ではなく、信頼関係を構築するための戦略的なスキルです。この記事で紹介した表現は、実際のビジネスシーンで即座に活用できる実践的なフレーズです。
文化による違いを意識することは重要ですが、「人として相手を理解しようとする姿勢」は普遍的な価値を持っています。最初は不自然に感じるかもしれませんが、繰り返し使うことで自然に使えるようになります。
不安な場面や重要な局面では、プロの通訳・翻訳サービスを活用することで、適切な表現を学びながら、徐々に自信をつけていくことができます。グローバルビジネスでの成功は、このような小さな積み重ねから始まります。今日から、一つでも新しい共感表現を実践してみてください。
海外の方とのビジネスシーンに「OCiETe通訳」
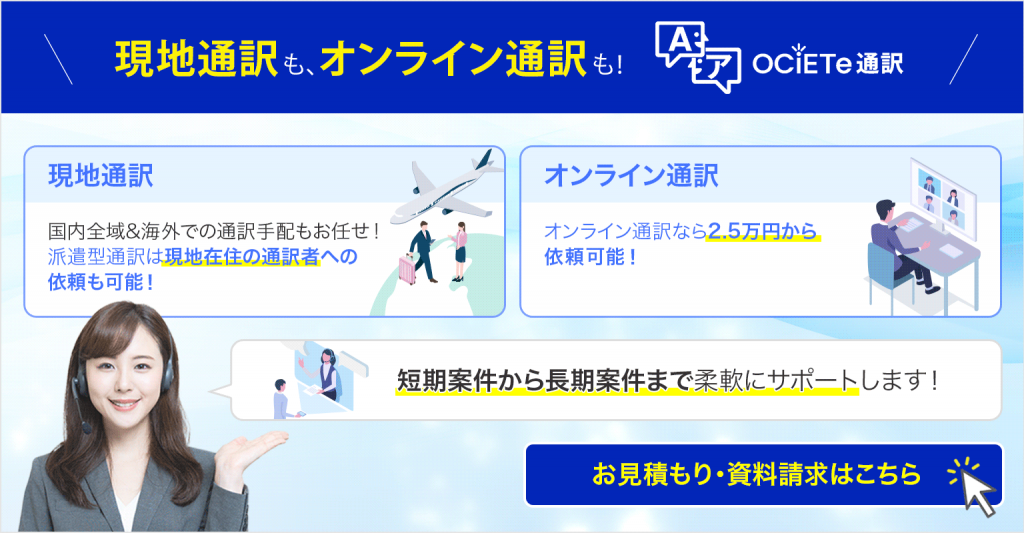
OCiETeは外国人クライアントとの円滑なコミュニケーションをお手伝いいたします。会食への同席や、会食会場までのアテンド、観光など様々なおもてなしシーンで通訳者の同行が可能です。
言語のみならず、クライアントの出身国から文化背景に配慮した上で、ホスピタリティあふれる通訳サービスをご提供いたします。
その他、商談時や海外出張時の通訳サポート、自社や商品サービスの説明に欠かせない会社案内や企画書の翻訳、海外進出サポートまで、幅広いお悩みにお応えします。
コーディネーターが、業界や商品・サービスごとに精通した担当者をシーンや用途に合わせ、ご案内いたします。お気軽にお問い合わせください。