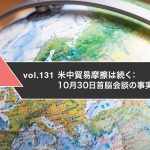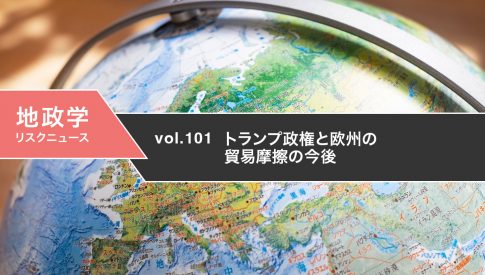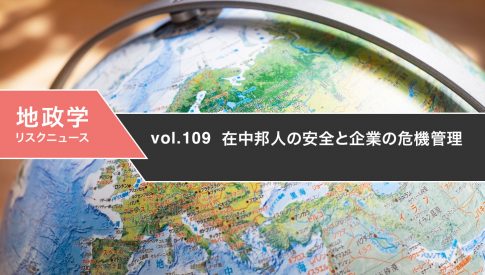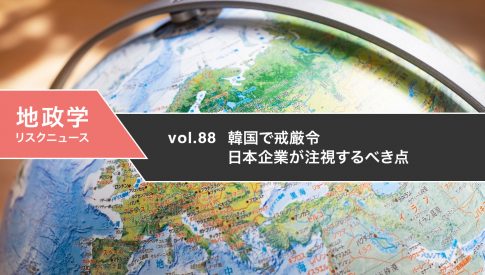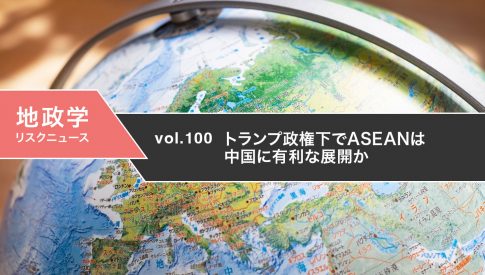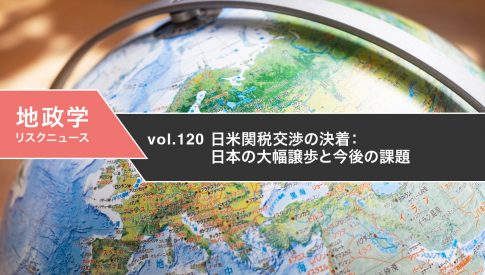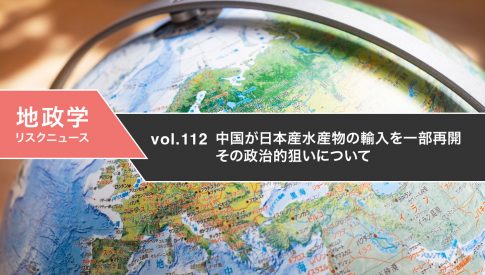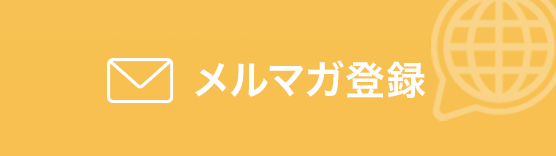エクスレバン
これまで渡航した国は40カ国以上 大学時代から国際経済を学び、現地に赴いて調査を行ったり、政治や経済について執筆活動を行っている。趣味はサーフィンと妻とショッピング。コロナ禍が終わりを迎えるなか、今後は中東やアフリカ方面への現地取材を検討中。
※掲載記事につきましては調査時、投稿時に可能な限り正確を期しておりますが、時間の経過とともに内容が現状と異なる場合がございます。
※掲載記載の内容は、弊社の立場や意見を代表するものではありません。
※提供する情報を利用したことによって引き起こされた損害について、弊社は一切の責任を負いません。
2025年10月、高市早苗氏を首班とする新内閣が発足しました。憲政史上初の女性首相として、高市氏は安倍晋三元首相の政策方針を継承し、外交・安全保障分野において米国との関係のさらなる深化に注力する姿勢を鮮明にしています。
この強固な対米重視外交は、日本の国益と安全保障の強化を目指す一方で、中国との関係に大きな緊張をもたらす可能性が高く、今後のアジア太平洋地域の情勢に重要な影響を及ぼす可能性があります。

米国との連携を強化
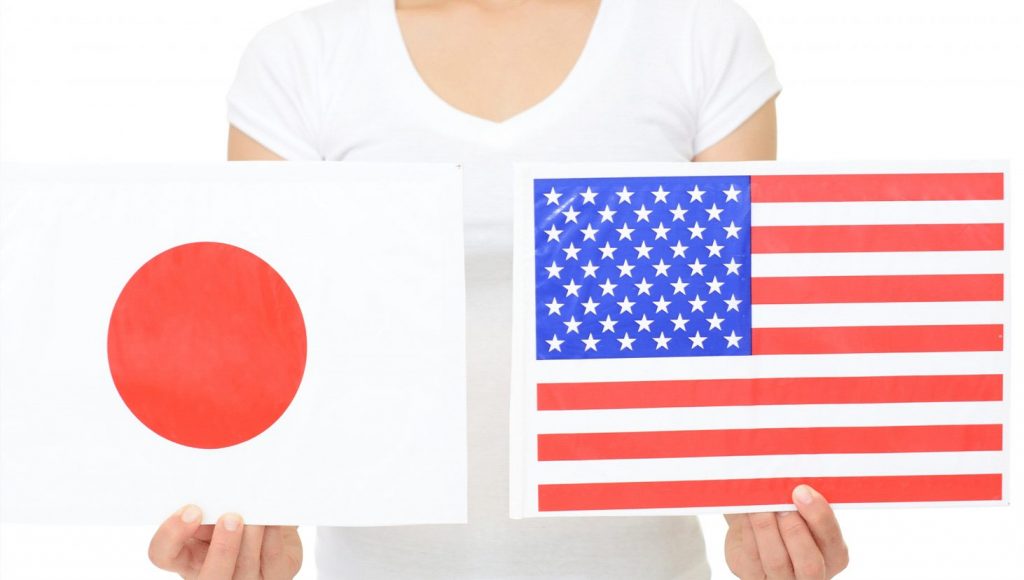
高市首相は、「強い日本経済」と「外交・安全保障で日本の国益を守り抜く」という強い決意を表明しています。この方針は、中国の台頭と国際情勢の不確実性が高まる中、日米同盟を外交・安全保障の基軸としてこれまで以上に重要視することを意味します。
具体的には、安全保障関連3文書の改定を前倒しで指示し、防衛費のGDP比2%増を視野に入れた防衛力強化を推進する方針です。これは、米国が求める役割分担の拡大に応えるものであり、同盟の信頼性を高めることにつながります。また、経済安全保障の分野においても、半導体や重要技術のサプライチェーン強靭化、機密情報の保護といった点で、米国との連携を強化すると見られます。
高市氏のこれまでの保守的な政治姿勢や、中国に対して一貫して強硬な発言をしてきた経緯は、米国共和党のタカ派層、特にトランプ大統領の支持者との親和性が高いと見られており、政権間のトップレベルでの関係構築がスムーズに進む可能性があります。日本は、トランプ政権が要求したとされる防衛費の増額に応え、「自由で開かれたインド太平洋」構想を牽引する主要なパートナーとして、米国との協調路線を一段と強固にしていくでしょう。
中国との関係は
一方で、高市政権の対米重視、保守的なイデオロギー、そしてタカ派的な外交姿勢は、中国との関係においては「冷え込み」を招く可能性があります。
靖国神社参拝をはじめとする歴史認識に関する高市氏の言動は、中国側から度々批判の対象となってきました。また、高市氏が台湾との関係を重視する姿勢を見せていること、そして日本の防衛力強化の方針は、中国にとっては面白くない話です。実際、高市首相の就任時には、中国指導者から祝電が送られないという異例の事態が発生しており、中国側の警戒感が読み取れます。
まとめ
これまでの日中関係において、対中窓口の役割を果たしてきた公明党が連立を離脱し、新たに日本維新の会が連立入りしたことで、政権内の対中政策に慎重な声が相対的に減少し、対立を回避するための人脈やパイプが小さくなることが懸念されます。
中国政府は高市政権に対し、日中共同声明などの政治的な約束を守り、理性的な対中政策をとるよう求めていますが、日本の国益を最優先する高市氏の外交路線が、中国側の要求と折り合う余地は小さいかもしれません。経済的な結びつきは維持する必要があるものの、政治・安全保障面での緊張は高まり、両国関係は「政冷経温」からさらに冷え込む可能性が高いとも言えます。